

1930年、東京に生まれる。国立音楽大学声楽科卒業。1953年より評論活動を始め、雑誌各誌に新譜月評寄稿する。その著書は多数。
指揮活動は、跡見女子大学合唱団常任指揮者をつとめる他、オーケストラを定期的に指揮し、その演奏はCD化されている。近年はアンサンブル・フィオレッティとの共演も好評を博し、話題を呼んでいる。
アンサンブルSAKURAとは過去8回の演奏会を経て、今回のベートーヴェン/交響曲3番「英雄」は3回目の挑戦である。
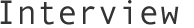
| ■演奏会のプログラムから |
 |  1930年、東京に生まれる。国立音楽大学声楽科卒業。1953年より評論活動を始め、雑誌各誌に新譜月評寄稿する。その著書は多数。 指揮活動は、跡見女子大学合唱団常任指揮者をつとめる他、オーケストラを定期的に指揮し、その演奏はCD化されている。近年はアンサンブル・フィオレッティとの共演も好評を博し、話題を呼んでいる。 アンサンブルSAKURAとは過去8回の演奏会を経て、今回のベートーヴェン/交響曲3番「英雄」は3回目の挑戦である。 |
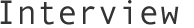 | |
| ■ | 増田(以下M):今回の演奏会についてのインタビューなんですが、いくつかお伺いしたい点があります。まず今回、エロイカは宇野先生との3回目の演奏になりますが、表現自体がいろいろと変わっている事もありまして、今回、宇野先生がエロイカをやりたいと思われた理由をお聞かせください。 |
| ◆ | 宇野先生(以下U):ボクが言い出したんだっけ? |
| ■ | M:随分前になりますけども、宇野先生とサクラのエロイカは定番の様にしたいと言っていた事は一度ありました。 |
| ◆ | U:忘れましたね。特にそういう風には思っていない。 |
| ■ | M:1回目(96年)でうまくいかない点があって、大阪公演(2000年)でそういったものをいろいろ修正しましたね。それから今回3回目になりますけど。 |
| ◆ | U:前2回は1st Vnの2楽章の最初のテーマがうまく弾けていないんですよ。リズムがね、ものすごく寸詰まりになったり、遅れたり。今回、その部分はうまくいってるんだ。それだけでも嬉しい。 |
| ■ | M:そうすると前2回でうまくいってなかったところを…。 |
| ◆ | U:テーマぐらいはなぁ、ちゃんと弾けるように…。強いところは皆うまいんだけど。ああいう、裸になって弦がものを言っている、そういうところをまず直す。 あとの−つは、僕が前2回でやりすぎているね。でも、ファンは「やりすぎていない」って、「冗談じゃない、あれをやめられちゃ困る」って言うんだ…。ファンの為に演奏するのは事実だけど、やっぱり自分としては大げさなところを引き締めていきたい。特に第1楽章でね。 |
| ■ | M:それは先生が録音を聞かれて、そのように感じられると。 |
| ◆ | U:そうなんですよ。だからねえ、僕の言っている事が必ずしも正しいとは思わないけど。だいたい録音ってもの生とは違うからね。だけど指揮者としては録音を頼りにするしかないんですよ。 |
| ■ | M:そうですね。 |
| ◆ | U:僕は自分の演奏を客席では聴けない。録音だけで聴いていると、ちょっとやりすぎているなっていうね。批評家の耳っていうか、レコード批評家の耳としてね。自分の欠点が見えてしまう。欠点と長所は紙一重というか、裏と表なんだけれどね。小説家でも無駄
なところを省いてゆくでしょう。 作曲家もそうですね。涙をのんでけずってゆくと良いものが出来る。演奏家も同じじゃないかな。少なくとも、僕は録音を信じてやるしかないんですよ。録音というものが発明されてしまった以上、これは仕方がないんだよ。 |
| ■ | M:やはり、録音が残るという事を前提に演奏するとお考えになられていると。 |
| ◆ | U:いや、今度は録音が残るかどうかわからないですよね。だから今は前提にしてないです。ただ自分として納得できるようにね。変なところを直して、リズムとかフレーズとか、少しでも古典派に近づけたいです。エロイカは書法が古典派だから。形はロマンだけれど。 |
| ■ | M:やはり表現がだいぶ新しく変わっていますよね。弾いている私たちとしても変わってるという実感があります。 |
| ◆ | U:とにかくベートーヴェンの楽譜っていうのは、読めば読むほど奥が深いですからね。本当は楽譜通 りが良いのかもしれないね。 |
| ■ | M:例えば、冒頭のpでsfが付いているところがありますね。あそこは今はfのsfでやってますね。 |
| ◆ | U:いや、強いアクセントをつけて、すぐに弱くするんだ。sfが生きないから。sfがないベートーヴェンというのは、骨のない傘みたいなもんでね。きつく弾いてスッと弱くすると古典派になると思う。 |
| ■ | M:ああ、そうですね。 |
| ◆ | U:…やはり指揮者は漫然とやる訳じゃないから、自分なりに人がどう思おうと、少しでも理想に近づきたいと思うでしょ。皆そうだと思いますよ。 |
| ■ | M:朝比奈先生なんかも、随分楽譜に頼っているじゃないですか。 ああいう心情っていうものはやっぱりわかりますか? |
| ◆ | U:ああ、ものすごくわかりますね。共感する部分がすごくありますね。むしろフルトヴェングラーとかワルターとかは、「ここは主題、ここは伴奏。」というふうにやる。僕もプラハではやっているけれどね。朝比奈先生はそれを止めちゃった訳ですけれども、あれはあれでものすごい。世界中にないスタイルですよね。ドイツ風ってのは嘘ですよ。ドイツっていうのはいろいろと、こうバランスをとるでしょう。 |
| ■ | M:テーマが出て来る時、伴奏はおさえたりとか。 |
| ◆ | U:今日の練習でプラハをやったけれども、モーツァルトはともかく、ベートーヴェンの場合はそんなにバランスをとってないでしょ?もっと、こう、朗々と鳴っている方が良いんですよ。スクロヴァチェフスキが最近、僕には少し物足りない。それはね、あまりにも主題・伴奏・主題・伴奏って、細かく工夫するからスケールか小さくなる。フルトヴェングラーも時々物足りないのは、それがあるから。ドイツ教養主義の…。 |
| ■ | M:刻みをおさえたりとか、ちょっと物足りない時はありますよね。 |
| ◆ | U:あまりにもすっきりしすぎちゃうんだな。響きはフルトヴェングラーってすこいんだけど。 |
| ■ | M:そうですね。ところでエロイカは3回目で、私たちも先生の表現に慣れてる部分もあるんですが、モーツァルトのプラハは先生にしても私たちにしても、新しいレパートリーになりますが、プラハという曲に関して、先生は思い入れはありますか? |
| ◆ | U:非常に好きですね。今ね、39とか36とかは、まずやりたくない。35はやっても良いけど、別 にやらなくてもね…。やっぱり今やりたいのは38、40、41。今回初めて指揮できて、とても嬉しいですね。これはすごく良い曲でしょ。これをね、のんべんだらりとやりたくない。安全運転とか。それをやってればもちろん安心ですよ。第1楽章も第3楽章もね…。でもそういうモーツァルトはやりたくないなあ。 |
| ■ | M:どちらかと言うと、アプローチからすると、以前に私たちがやった25番に近い、ああいう感じなんですね。 |
| ◆ | U:まったく同じですよ。基本的にはジュピターも同じですよ。 |
| ■ | M:激しいわけですね。 |
| ◆ | U:いわゆる、エレガントなウィーン風っていうのは、どうも好きじゃない。 |
| ■ | M:最近のモーツァルトの演奏が、古楽器風の演奏が出てきてますよね。 |
| ◆ | U:皆、古楽器風ですよね。現代楽器指揮者のな生ぬ
るさがない。 でも、あそこまでトランペットを強奏させるのは趣味じゃないですね。今までの古いスタイルの中で、どれだけ生命力のあるモーツァルトにするか。 |
| ■ | M:ちょっと話が変わりますが、先生が今お持ちになっているのは、ベーレンライターの新しい版の。そこに意図は…? |
| ◆ | U:無いね。 |
| ■ | M:無いですか。 |
| ◆ | U:他のを持ってないだけ。できれば旧いのがあれば使いたい。 |
| ■ | M:探してきましょうか? |
| ◆ | U:いいよ。もう慣れたから。 |
| ■ | M:ブライトコプフではボーインクなどが書かれていますが。 |
| ◆ | U:僕が変えている所はありますか? |
| ■ | M:若干ありましたね。 |
| ◆ | U:でもそれは僕がこっちの楽譜(べ一レンライター版)にとらわれているという訳じゃないですね。例えば、リズムがパッと切れるところは切りたいからね。それが出来るか出来ないかで随分違うなぁ。…でも、SAKURAはよくやっている方じゃないですか?普通 はあそこまで細かくやらないですよ。もうちょっと無難にやった方が指揮者も楽だし、皆も楽だし。僕は追い込んでいくからなぁ。 |
| ■ | M:演奏している方は確かに…。 |
| ◆ | U:大変でしょ。 |
| ■ | M:やっている方は面
白いですけどね。 ところで、ここのところ、モーツァルト、べ一トーヴェンという形が続いておりますが? |
| ◆ | U:いや、僕は変えようと思って、新世界をやったりブラームスの1番をやったりしてきた。いつも、モーツァルトは良いとして、ベートーヴェンぱっかりじゃね。まだ4、6だけやってませんね。でも、あとは全部やったんだから、ロマン派にいきたいなぁ。いずれフラームスの3番とか。それと、僕が80歳になる前にもう−度第九をやりたい。80前というと、来年77でしょ。来年は他の曲だから、再来年かその次しかない。 |
| ■ | M:第九は先生、随分ご執心じゃないですか。 |
| ◆ | U:第九はそれこそ定期的にやりたいけど、お金がかかるし。弦も人がいないと。ホールも音響が良いところね。前回の所沢は悪かったね。 |
| ■ | M:エロイカは、修正しながら演奏していきたいという話かありましたけれども、第九もプロのオケとも演奏されていますけど、やっぱりそういった部分もあるんですか? |
| ◆ | U:第九はやりすぎたところはない。やり足りないところはある。 フィナーレのコーダはちょっとブレーキをかけているんですけどもね。メチャクチャになると格好悪いから。 |
| ■ | M:フルトヴェングラーみたいに? |
| ◆ | U:あそこまではいかないけどね。でもああいう表現で音がちゃんと鳴ったらすごいと思う。あれ、鳴りますよ。フルトヴェングラーが下手なんですよ。 |
| ■ | M:最後はちょっともったいないですよね。 |
| ◆ | U:あんなメチャクチャな。プロの指揮者とは言えませんよ、あれ。 佐藤眞がいつも怒るんだよ。あのテンポでもちゃんと弾けるよって。弦は刻んでるだけだから。あそこで落っこちるなんてことありえない。 |
| ■ | M:確かにそうですね。 |
| ◆ | U:それを落としている訳だから。 |
| ■ | M:最後が鳴ってないですよね。最後の和音がもったいないですよね。 |
| ◆ | U:練習でちゃんとやれば出来るんですよ。ただ、出来たら出来たでね、あまり速い感じがしないんですよ。ことによると、あの人の考えが、ああいう風にメチャクチャになる事を想定していたのかもしれない。そうだとすると、ものすごい事なんだよ。崩壊させちゃうんだから。 |
| ■ | M:なるほど。そういう考えもありますね。 |
| ◆ | U:あるでしょ、プロの指揮者だもん。 |
| ■ | M:他の曲であんまりああなってることってないですもんね。 |
| ◆ | U:第九の最後だけ。ザルツブルクでやった演奏は、シンバルに全部消されてる。変な人だね。でもフルトヴェングラーを聴いちゃうと他の指揮者は全然物足りないね。 |
| ■ | M:では、SAKURAでもう一度、第九を…ということですね。 |
| ◆ | U:再来年あたりね。何とかやりたいね。 |
| ■ | M:考えておきます。 今日はお疲れのところ本当にありがとうございました。では先生、次回の練習は5月の最後ですよね。(このインタビューは4/30に行われた。) |
| ◆ | U:今日はプラハでしたが、今の時点での出来具合はどうですか。 |
| ■ | M:どうでしょうかねえ。悪くはないですね。え−っと、75%くらいですか。もう少し先生の求めているテンポに慣れないといけませんねえ。 |
| ◆ | U:速すぎますか? |
| ■ | M:大丈夫です。 |
| ◆ | U:それで安心です。 |
| ■ | M:それは皆が感じれば。エロイカの方はそんなに心配ないかもしれませんね。全体的に。 |
| ◆ | U:そうですか。プラハが心配ですか? |
| ■ | M:慣れるまでにちょっと。安定するまでに。 |
| ◆ | U:これからもう、プラハだけを練習する日が無いんだよ。今日に僕はかけていたからね。次回はエロイカにかけますよ。 |
| ■ | M:はい、ありがとうございました。 |
| (聞き手:増田光一/文:渡辺真史) |
|
|
| ◆前のページへ戻る |